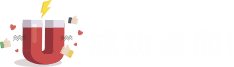2025年07月01日
BtoB企業におけるAI時代のコンテンツ戦略 - 一次情報と Thought Leadership(ソート・リーダーシップ)で「ゼロクリック検索」の壁を突破する-

2024年8月、日本でも Google 検索の AI Overviews(※1)が公開され、2025年5月には200超の国・地域へ公開されました。
検索結果上部を「AIによる概要」が占有した結果、BrightEdge の調査(2025年5月 米国)によると、自然検索のCTR(※2)が前年比30%低下し、Webサイト流入は急減しています。
さらに Google は「AI Mode」(※3)を米国で提供開始し、6〜12カ月内に日本語対応することを予告しました。検索者がWebサイトを訪れない「ゼロクリック検索(※4)」時代に、企業がリードを獲得し続けるには、一次情報に投資し、AIにも引用される「原典」ポジションを築くことが不可欠です。
本記事では、BtoB企業におけるAI時代のコンテンツ戦略について、詳しく解説します。
※1 AIOs AIによる概要。検索上部に生成AIが回答概要を表示する機能。以降、AIOと表記。
※2 CTR Click-Through Rate=表示回数に対するクリック率。BrightEdge 調査(2025年5月 米国)で AIO が出現する検索語句の平均 CTR が30%減。
※3 AI Mode AIモード。Google 検索に統合された対話型 AI 機能で、検索と会話を往復できる新モード。
※4 ゼロクリック検索 ユーザーが、検索結果一覧の上部に表示される情報のみを見て満足してしまい、一覧表示されているコンテンツのURLをクリックせずに離脱してしまうこと。Search Engine Land 調査(2024年 米国)で約60%を占めると報告。
目次
- 現状の課題:従来のSEOモデルの崩壊
- 解決策:一次情報特化によってAIに引用される「原典」ポジションを築く
- 目指すべき姿:Thought Leadership の確立
- まとめ
1.現状の課題:従来のSEOモデルの崩壊
リードジェネレーションを支えてきた従来型のSEO が、Googleロジックの変化によって急速に機能不全に陥っています。
「Webサイトへの流入が激減している」「このままでは、リードが獲得できなくなるのではないか」「そして、これからますます、その傾向は強まるのではないか」・・・これは多くのBtoB企業のマーケッターが抱えている危機感です。その原因は、主に以下の3つです。
1.1 検索アルゴリズムの高度化
Google は 2024年3月のアップデートで低品質・未編集コンテンツを45%削減したと発表しました。
これは、Google のランキングシステムのひとつであるHelpful Content System(※5)の強化によるものです。
1.2 AIO 表示率の急増
AIOは、米国での一般公開後、日本を含む100超の国・地域で展開(2024年10月 Google 公式)され、さらに2025年5月には200超の国・地域へ拡大しました。
Semrush 調査(2025年3月、米国)では、AIO 表示率が1月の6.49%から3月に13.14%へ倍増。AIが要約を提示する頻度が増え、BrightEdge の調査(2025年5月 米国)によると、AIOが出現する検索語句では、CTRが平均30%低下しています。
1.3 AI Mode の登場
Google I/O 2025 の発表によると、AI Mode は英語圏で先行し、6〜12カ月内に日本語など主要言語へ拡大予定です。
AIが文脈を理解し、複数の情報源を統合して、会話形式で情報を提供してくれるようになることで、Webサイトを経由しない情報取得がさらに加速することが予想されています。
上記3つの要因によって、「AIによる量産記事生成のような従来型のSEO は、近い将来意味を持たなくなるだろう」と多くのマーケッターが予測しています。
※5 Helpful Content System ヘルプフルコンテンツシステム.
独自性と実体験を重視し低品質ページを除外する Google アルゴリズム(2022年導入、2024年3月改訂)。
2. 解決策:一次情報特化によってAIに引用される「原典」ポジションを築く
従来のSEOモデルが崩壊しようとしているいま、BtoB企業のマーケッターが新たなコンテンツ戦略を描くために押さえておくべき5つのポイントを、以下で詳しく解説します。
2.1 「クリックしないユーザー(ゼロクリック・ユーザー)」と、「クリックするユーザー」の違い
「ゼロクリック検索」が急増しているにも関わらず、「いまのところ、リード獲得には大きな影響が出ていない」という話もよく聞きます。それはなぜなのでしょうか?
Cube Creative(2025年3月 米国)は、"ゼロクリックは主に「〜について知りたい」という情報収集型の検索に影響する。取引を想定した検索にはあまり影響しない" と指摘しています。
つまり、「ゼロクリック・ユーザー」は、「いままでも用語集などに流入し、すぐに直帰していたユーザー」と重なっているため、ビジネス的なインパクトは小さいと考えられているのです。
一方、株式会社PLAN-Bの調査(2025年6月 日本)によると、「生成AI検索で表示された引用をきっかけに訪問したWebサイトやメディアにて、次のような行動をとったことがありますか?」という質問に対し、「商品やサービスを購入した」が24.9%、「メールマガジンや資料をダウンロード・登録した」が22.4%、「問い合わせをした」が21.4%と、何らかの具体的アクションにつながっているという結果が出ています。
筆者も、実際に、愛用していたファンデーションメーカーが日本撤退をした際に、代替品を検索し、「AIによる概要」に表示された全く知らないメーカーから代替品を購入した経験があります。
このように「買う気のあるユーザー」は、生成AI検索が表示した回答を読んで終わりではなく、その引用元をクリックしている傾向が強いのです。
ですから、これからのコンテンツ戦略では、「AIに引用される原典」になることが重要です。
2.2 AIに引用される条件
では、AIはどのようにして引用するサイトを選定しているのでしょうか?検索エンジンで上位表示されていることが、必須条件なのでしょうか?
ChatGPT o3は、"出発点は検索エンジンだが「ランキング≠信頼度」。検索上位は"手がかり"と割り切り、すぐ一次情報へ遡る"と述べています(2025年6月現在)
ChatGPT 4oは、"「検索上位」だけを信用しないのは、SEOの影響や商業的意図によるノイズが入ることを知っているからです。" と述べています(2025年6月現在)
Geminiも,"検索エンジンに上位表示されていることは、トレーニングデータに含まれる情報源を選定する際の主要な基準ではありません。最も重視されるのは、情報の質です。"と述べています(2025年6月現在)
つまり、「AIに引用される原典」として、検索エンジン上位表示は必須ではなく、「AIに発見してもらうきっかけになる」程度の影響しかないということです。
では、AIが情報を引用するかどうかを判断する主な基準は、何なのでしょうか? 生成AIの種類によっても多少異なりますが、共通して重要視しているのが、以下のような項目です。
① 一次情報のソースであること(信頼性)
② データや根拠が示されていること(透明性)
③ 新しい情報であること(最新性)
④ 他の信頼できる情報源と大きな矛盾がないこと(整合性)
⑤ その分野で認知度や権威のある専門サイト、専門家の解説であること(専門性・権威性)
2.3 一次情報とは何か?
一次情報とは、自身が直接体験、または調査や実験をすることで得られた情報のことを指します。
企業発信のコンテンツとしては、「導入事例」「専門家インタビュー」「調査レポート」などが、一次情報にあたります。
それに対し、二次情報とは、一次情報を引用したり参照したりして作成された情報のことを指します。
従来のSEOモデルで量産されていた「Webリサーチを元にして作成された記事」や、「AIが生成した記事」は、全て二次情報にあたります。
2.4 なぜ、既存のコンテンツに頼る情報発信はリスキーなのか?
独自性の高い情報をイチから生み出していくよりも、既存の情報を寄せ集め・加工編集して記事を生成する方がコストも手間も時間もかからないことから、いままでは一次情報の制作・発信に消極的な企業も少なくありませんでした。
しかし、既存のコンテンツに頼る情報発信は非常にリスキーです。
なぜなら、AIや検索エンジンは、「同じ内容を複数URLで拾った場合に、どれか1件だけを残して他を落とす」仕組みを搭載しているからです。
つまり、似たような記事がいくつあっても、AIや検索エンジンは、全ての類似記事・引用記事の大元になった原典記事しか残さないということです。
Semrush データ(2025年3月 米国)でも、"高品質な一次情報ページは、「ゼロクリック検索」時代においても可視性(ユーザーの目に触れること)を維持しやすい傾向がある"と述べています。
2.5 一次情報発信モデルに転換するために必要なアクション
では、従来型のSEOモデル から一次情報発信モデルに転換し、AIや検索エンジンからの引用性を高めるためには、具体的にどのようにしたらいいのでしょうか?
2.5.1投資ポートフォリオの見直し
従来型のSEOに投じていたリソースを、「導入事例」「専門家インタビュー」「調査レポート」などに再配分し、AIや検索エンジンに引用される一次情報を創出していきましょう。
2.5.2 「少数 × 高価値 × 継続」モデルの構築
高品質な一次情報を、継続的に発信するモデルを構築しましょう。
継続発信することによって、「最新性」「整合性」を高めることができるだけではなく、外部被リンク・指名検索を蓄積することもできます。
3. 目指すべき姿:Thought Leadership の確立
AIに「その分野で認知度や権威のある専門サイト、専門家の解説である」と認識してもらうためには、一次情報を継続発信するだけではなく、企業が、その業界における Thought Leadership (※6)を確立していると認知されることが重要です。
※6 Thought Leadership 業界の未来像を語り、信頼される知的リーダーとして発信する企業姿勢。Forbes 記事(2025年6月 米国)で BtoB に不可欠と指摘。
3.1なぜThought Leaderと認知されることが重要なのか
Search Engine Journal (2025年3月 米国)は、"生成系検索は、出典として E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)スコアの高いドメインを優先的にリンクする傾向を示す。"と述べています。
そして、SEOの専門家である住太陽氏は、「E-E-A-Tとはサイトや著者の経験、専門性、権威性、信頼の評価」という記事の中で、 "E-E-A-Tの向上について押さえておきたいポイントは、経験や専門性や権威性や信頼といったものは自分でアピールするだけでは十分ではなく、サイテーションや被リンクといった外部からの評判情報で裏付ける必要があるということです。"と述べています。
つまり、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)スコアの高いドメイン=第三者からその分野の権威であり専門家であると認知されている企業=「Thought Leader」といえるでしょう。
3.2 Thought Leaderを目指すメリット
Thought Leaderを目指すメリットは、「AIに引用される原典ポジション」を得られることだけではありません。他にも、Web内外でのメリットが考えられます。
3.2.1 「専門家」としての認知効果
一次情報が AIO や AI Mode の回答根拠に採用されると、ユーザーの目に触れる機会が増えるので、ユーザーは、その企業名を最初に認知した時点から、「その道の専門家」として認識することになります。
それによってユーザーの信頼度が上り、商談化までのハードルが下がることが期待できます。
3.2.2 権威づけの複利効果
Thought Leaderが発信する高品質な一次情報は、Web上で繰り返し引用・参照されるため、被リンクやSNSでの言及が雪だるま式に増加します。それに伴い、検索順位も上昇します。そして、AIもその情報を学習し続けるため、権威づけが自己強化されていきます。
3.2.3 企業価値の向上
Thought Leadershipの確立を目指して、自社ならではの情報を継続的に発信することで、顧客や投資家、優秀な人材から「この業界をリードする会社だ」と認めてもらえるようになります。そうなれば、価格だけで勝負するような厳しい競争から抜け出し、信頼されるブランドを築けます。
また、社内においても、「調べ、学び、発信する」文化が根づくことで、イノベーションのスピードが上がり、社員のやる気を高め、退職を防ぐ効果も期待できます。
さらに、オープンに情報を公開することで、他社との協業が生まれ、新しい市場への進出や収益源の多様化が進む可能性もあります。
最終的には、株価評価やESGスコアといった企業価値の指標も向上し、持続的な成長のサイクルを実現できるようになるのです。
3.3 Thought Leadershipを獲得するための指針
AIや検索エンジンに「業界のThought Leaderである」と認知してもらうためには、
・一次情報を継続的に発信する
・執筆者の略歴・資格を明示する
・業界誌に寄稿する/業界団体のセミナーに登壇する
のような「日々のアクション」の積み重ねも、もちろん重要です。
しかし弊社は、その前に、「Thought Leaderに値する企業文化の構築・浸透」こそが重要であると考えています。
情報発信が、企業文化に根差したものでなければ、それはただの「外向けのパフォーマンス」に留まってしまい、いずれ「真のThought Leader」にポジションを奪われてしまうからです。
弊社が考える「Thought Leaderに値する企業文化の構築・浸透」の進め方については、こちらをご覧ください。
4. まとめ
• AIO の普及と AI Mode の登場で、「従来のSEOモデル」は限界を迎えつつあります。
• 「従来のSEOモデルの崩壊」に備える鍵は、企業固有の一次情報を継続的に発信し、「引用される原典」に育てることです。
• 「引用される原典」に育てるためには、「Thought Leaderに値する企業文化の構築・浸透」こそが重要です。
執筆者:株式会社グリーゼ 代表取締役 江島民子(えじまたみこ)
富士通系のシステムエンジニアを経て、2000年に会社設立。以来、一貫してコンテンツマーケティングに取り組んでいる。
日経MJ、ECzineなどに寄稿・連載多数。
宣伝会議主催「メールマーケティング実践講座」「BtoB企業のためのメールマーケティング実践セミナー」講師。
Salesforce 認定 Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント(旧:Salesforce 認定 Pardot コンサルタント)
株式会社グリーゼのコンテンツ制作ポリシーは、こちら https://gliese.co.jp/policy/
参考URL一覧
•New ways we're tackling spammy, low-quality content on Search(Google 検索公式ブログ, 2024年3月, 米国) https://blog.google/products/search/google-search-update-march-2024/
•Generative AI in Search: Let Google do the searching for you(Google 検索公式ブログ, 2024年5月, 米国) https://blog.google/products/search/generative-ai-google-search-may-2024/
•Ultimate Guide to AIOs!(BrightEdge, 2025年5月, 米国)
https://www.brightedge.com/ai-overviews
•Google AIOs data: Search clicks fell 30% in last year(Search Engine Land, 2025年5月, 米国)
https://searchengineland.com/google-ai-overviews-search-clicks-fell-report-455498
•AIOs Study: What 2025 SEO Data Tells Us(Semrush, 2025年3月, 米国)
https://www.semrush.com/blog/semrush-ai-overviews-study/
•Google introduces new 「AI mode」 function in renewed bid to revolutionise search(Euronews, 2025年5月22日, 欧州) https://www.euronews.com/next/2025/05/22/google-introduces-new-ai-mode-function-in-renewed-bid-to-revolutionise-search
•Google I/O 2025: AI Takes Center Stage with Gemini 2.5 and New Search Features(Arion Research, 2025年4月, 米国)https://www.arionresearch.com/blog/jdrld6pwiq3bnp2rr9sr70odyvkdh3
•Google Search AI Mode update(Google 検索公式ブログ, 2025年5月, 米国)https://blog.google/products/search/google-search-ai-mode-update/
•Nearly 60% of Google searches end without a click in 2024(Search Engine Land, 2024年7月, 米国)
https://searchengineland.com/google-search-zero-click-study-2024-443869
•Transforming Thought Leadership Into a Client Growth Lever - The Evolution of Thought Leadership in B2B(Forbes, 2025年6月20日, 米国) https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2025/06/20/transforming-thought-leadership-into-a-client-growth-lever-the-evolution-of-thought-leadership-in-b2b/
•Cube Creative 「Win at Zero-Click Searches: 6 Strategies for 2025」(2025年3月 米国) https://cubecreative.design/blog/partners/win-at-zero-click-searches-6-strategies-for-2025-1754
•株式会社PLAN-B(2025年6月 日本) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000325.000068228.html
•Search Engine Journal(2025年3月 米国) https://www.searchenginejournal.com/role-of-eeat-in-ai-narratives-building-brand-authority/541927/

【調査レポート】「一次情報を核にする」が55.1%-AI時代におけるBtoB企業マーケティング担当者の課題と対策-
生成AIの普及により、検索体験はAIが直接回答を示す形式へと変化しています。これによりコンテンツマーケティングは量の競争から質の競争に移行しました。本調査は、AI時代にBtoB企業のマーケティング担当者が感じている課題と対策を明らかにし、「一次情報×専門性×信頼性」を高める必要性を検証することを目的としています...